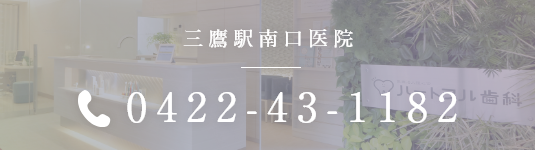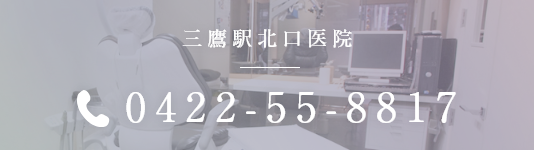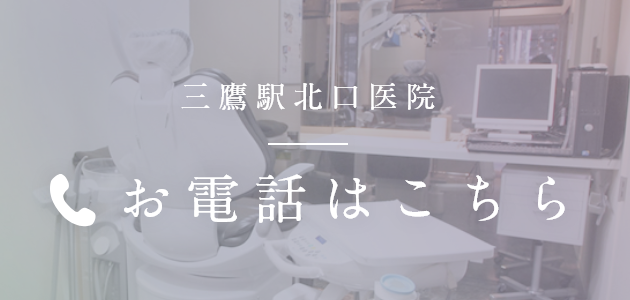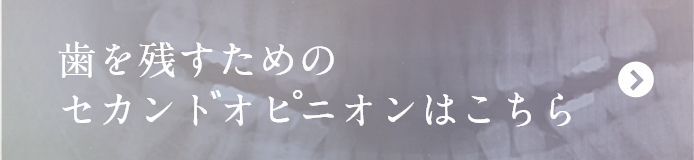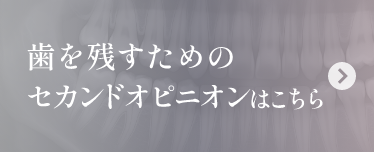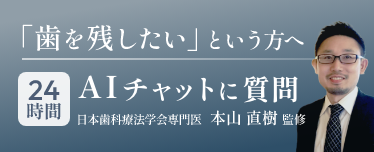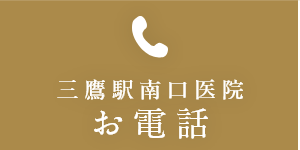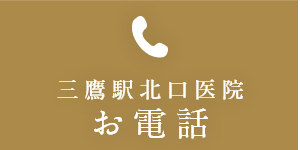第4回歯髄再生医療研究会 in 神戸①─「歯を残す治療」を未来へ!最前線で学んだ歯髄再生の進化─
こんにちは。
ハートフル総合歯科グループの歯科医師、本山 直樹と申します。
私は、歯内療法専門医の立場から根管治療における臨床症例を通して感じたことをブログに書いております。


先日、神戸で開催された「第4回歯髄再生医療研究会」に参加してまいりました。
今回は、理事長の下田先生とともに、全国の歯科医師が集う症例検討会に出席して、最新の知見を学ぶ機会をいただきました。
歯髄再生医療協会も発足から3年以上が経過して、現在では全国28の歯科医院で歯髄再生治療が実施できる体制が整っています。
“歯の神経を再生する”という選択肢が、少しずつ現実的な治療として広がってきていることを改めて実感しました。
歯髄再生医療研究会による症例検討会の目的は、臨床経験豊富な先生方による症例報告を通して、より実践的な技術を学びながら、課題を共有することにあります。
既に150例を超える臨床実績から「有効性」と「安全性」が確認されている一方で、根管内の無菌化や硬組織形成の安定化など、依然として技術的な挑戦が続いています。
私自身も過去の症例を振り返りながら、成功事例の多い先生方の助言を受けて、試行錯誤しながらスタッフとともに治療における改良を重ねてきました。


Opening Remarks(開会挨拶)
歯髄再生治療の全体症例のまとめ
RD歯科クリニック 中島 美沙子先生
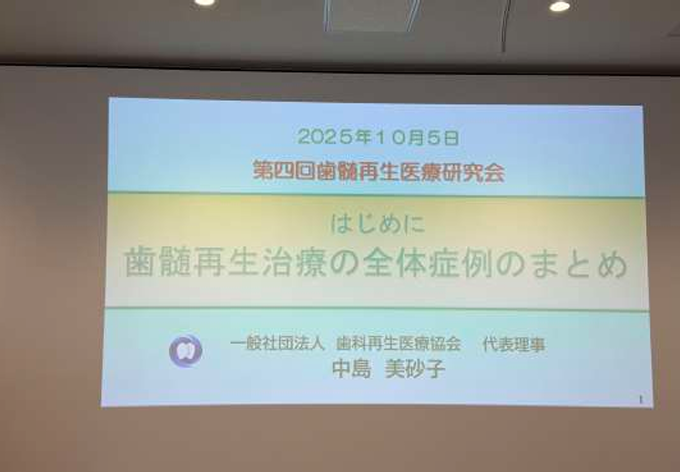

中島先生より、「歯髄再生治療の全体症例のまとめ」と題しまして、歯の粉砕物を用いた歯髄再生治療(象牙質再生治療)に関する最新報告を聞くことができました。
ハートフル歯科においても、最近「象牙質再生治療」に関する登録・申請に関して受理されたところです。
象牙質再生治療に関するブログ記事はこちら ↓
「歯の粉砕物を用いた歯髄再生治療」
「歯の粉砕物」が再生の鍵に!
抜歯された自分の歯を細かく粉砕して、再生過程の中で利用する非常に先進的なアプローチです。
多くの臨床で歯の粉砕物を併用する治療が進められており、成功症例では2~3mm厚の被蓋象牙質が形成されるとのこと。
特に吉橋先生の外傷例では、1年後に石灰化が明瞭に確認されて、正常象牙質の約80%に相当する硬組織密度が得られたとの報告がありました。
つまり、「人工的ではなく、自分自身の細胞が再び“歯を作る”」という現象が起きているのです。
一方で、途中でデンティンブリッジ(象牙質の橋)が形成されてしまう例も存在します。
しかし、このデンティンブリッジの形成自体が「歯髄細胞が活動している証拠」と捉えられ、象牙質が形成されるということ自体が、歯髄が生きて機能している証明であり、歯髄再生の過程を示す重要な指標であることが強調されました。
長期経過が示す“歯髄再生の可能性と安定性”
中島先生はさらに、5年経過した抜髄症例や4年経過した感染根管症例のフォローアップデータを提示されました。
いずれの症例も根尖病変は消失して、冷温刺激への反応も維持されているとのことでした。
CT解析ソフト「OsiriX」を用いた評価、体積測定では、根管壁への象牙質添加が確認されて、長期的にも機能が安定していることが明らかになりました。
これは、歯髄再生治療が単なる実験的な治療ではなく、確かな臨床成果
を伴う医療技術であるということが改めて分かる結果となりました。
患者層から見える今後の課題
症例データの集計では、興味深いデータとして歯髄再生治療を受けている患者の年齢層は25~50歳が中心であり、一方で50~60代では大幅に減少しているという報告もありました。
その理由として――
• 自家歯が少ない(50代で約85%、60代で約92%が自歯を喪失)
• 全身疾患(糖尿病・自己免疫疾患など)の影響
• 再感染根管治療の増加(無菌化への困難さ)、残存歯質量の低下
このような臨床的課題が挙げられます。
つまり、再生医療を受けたくても“材料となる自分の歯がない”というケースが増えているのです。
この現実は、私たちが「いつ・どの段階で歯を守るか」を考える上で非常に重要な示唆を与えてくれるものでした。
今後の展望と戦略ー歯を守るために、今できる選択ー
中島先生は、今後の展望として50~60代にも治療機会を広げるために、いくつかの方向性を提案されていました。
• 早期の「歯バンク保管」:
親知らずや矯正抜歯による便宜抜歯された歯を将来の再生医療に備えて保存する。
• 他家歯髄移植の臨床研究:
将来的には自歯がなくても治療が可能。自分の歯がなくても治療を可能にする臨床研究が進行中。
• 再生促進法の開発:
上部象牙質の形成を促し、咬合機能まで回復させる新手法。
• 除菌法の再検討:
難治性症例に対応する新しい滅菌プロトコルの提案。
• 中高年層への啓発:
「根尖病変は放置せず、免疫低下前に治療を」という早期治療の重要性についてのメッセージ発信。
これらの戦略を通じて、歯髄再生医療を“若い人だけの治療”ではなく、生涯自分の歯で噛みたい人すべての治療法として確立していく姿勢が示されました。
まさに“歯を残す医療の未来”をつくる取り組みに、心が動かされました٩( ‘ω’ )و
参加を通じて感じたことー学びを臨床に活かしてー
今回の症例検討会では、各先生方の実践的な報告を通じて、「現場のリアル」を学ぶことができました。
とくに、「成功症例の裏には、地道な無菌化・確実な封鎖・管理の徹底がある」――この事実を改めて痛感して、同時に臨床の本質を再確認しました。
歯髄再生は、材料や技術の進化だけでなく、一つ一つの工程の精度が最終結果を左右する治療です。
感染を徹底的に制御して、細胞が安心して“生きられる環境”を整えること。これらが成功の鍵であり、私がハートフル歯科で歯髄再生治療に取り組む上で最も大切にしている理念でもあります。
まとめ
歯髄再生治療は、もはや「夢の技術」ではなく、確実に実用段階へと進み、確かな選択肢になりつつあります。
これまで「神経を取るしかない」と言われてきた歯にも、生きた神経を取り戻す可能性がある。
私たち臨床医が症例を積み重ね、課題を共有しながら改良を続けることで、「歯を抜かない」「神経を残す」治療の未来がさらに広がっていくと感じました。
この最先端の医療を、安全にかつ確実に提供できるように、私たちも日々研鑽を重ねています。これからも学びを実践に活かして、患者さんに最善の選択肢を提供していきたいと思います。
今回の学びを明日からの臨床に活かして、
「できるだけ歯を抜かない・神経を残す」治療を、これからも三鷹から発信していきます。
歯髄再生医療研究会にて講演を通じて貴重な知見を共有してくださった中島 美沙子先生、また今回講演していただいた先生方、そして歯髄再生医療協会の皆様に、心より感謝申し上げます。
ありがとうございました( ́∀`)
他の先生方の講演についても、次回以降のブログにまとめさせていただきたいと思います。ご興味のある方はぜひ御一読下さい!
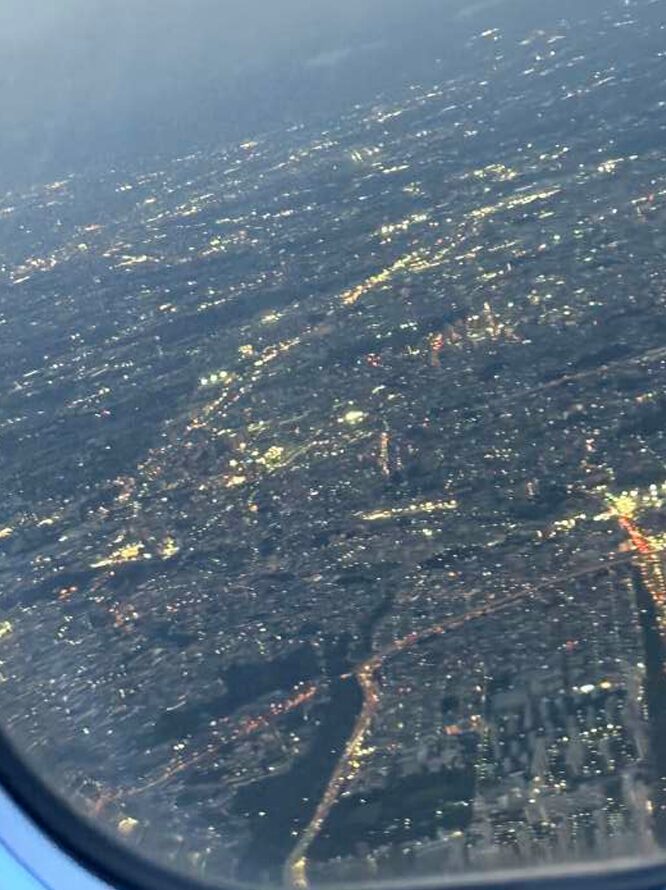
お問い合わせはこちらから↓
三鷹・東京で精密根管治療をお探しならハートフル歯科|無菌化で再発防止
本山 直樹