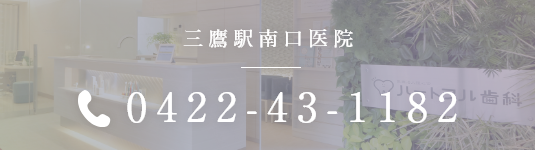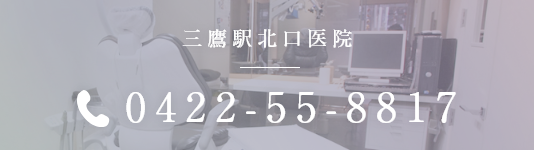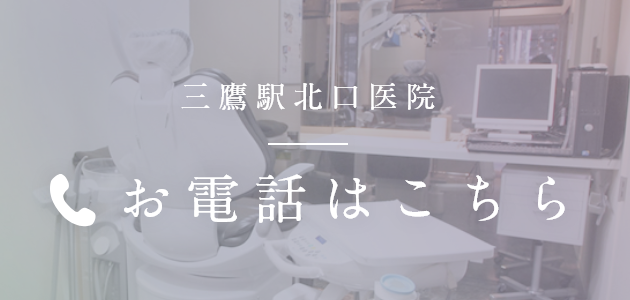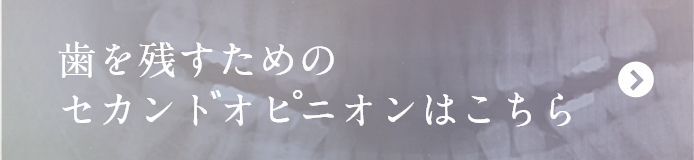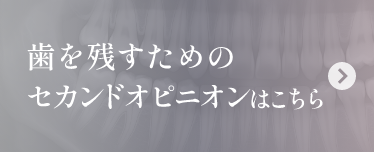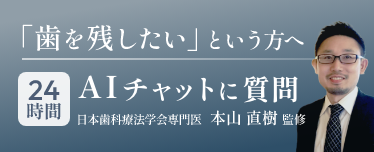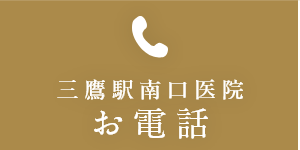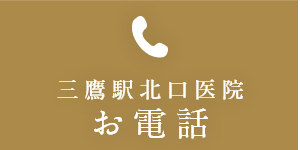【現地レポート】専門医が聴いて感じた「最新歯内療法術式」─時代は“歯髄再生”の実装フェーズへ
こんにちは。
ハートフル総合歯科グループの歯科医師、本山 直樹と申します。
私は、歯内療法専門医の立場から根管治療における臨床症例を通して感じたことをメインに学会参加、セミナー受講などについてもブログに書いております。
私は現在、日本歯内療法専門医を既に取得していますが、先日、自己研鑽のために学会認定臨床研修会(認定カリキュラムⅥ 「最新歯内療法術式」)を受講しました。
本来、学会認定臨床研修会における認定カリキュラムは、専門医取得のために毎年受講すべき必修カリキュラムになっております。
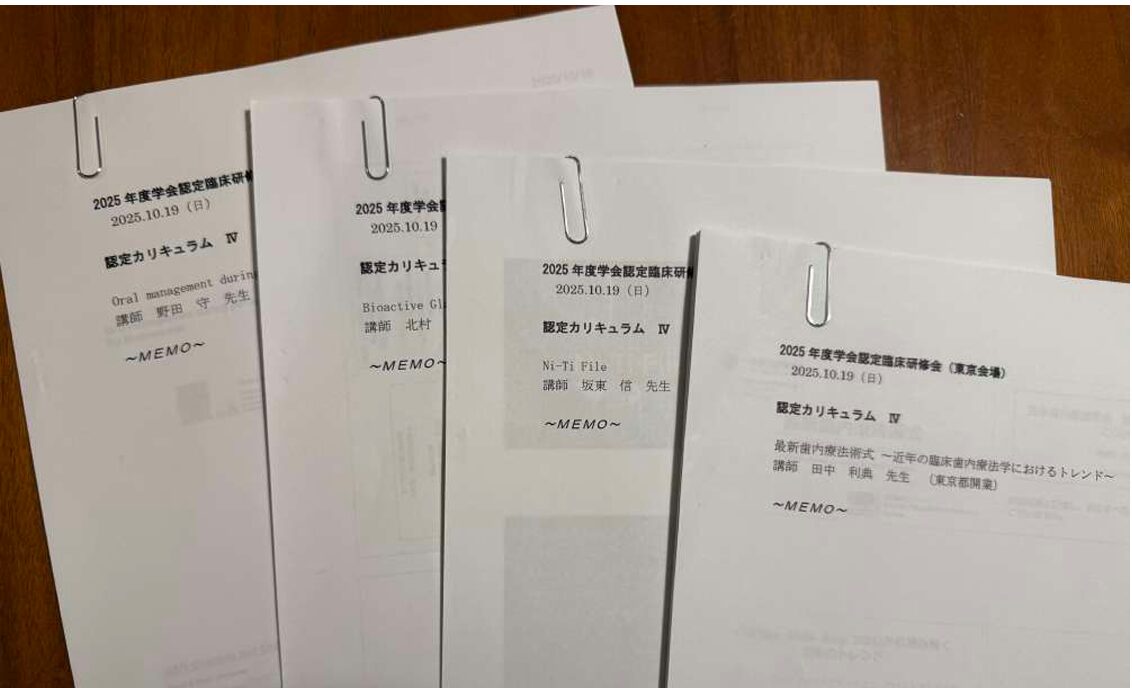
今回の研修会では、4名の先生方がそれぞれの視点から、最新の歯内療法における臨床的トピックや今後の方向性を共有して下さいました。
どの講演も非常に学びが多く、エンドドンティクスという分野が、確実に「再現性」「科学性」「再生医療」へと進化していることを実感しました。
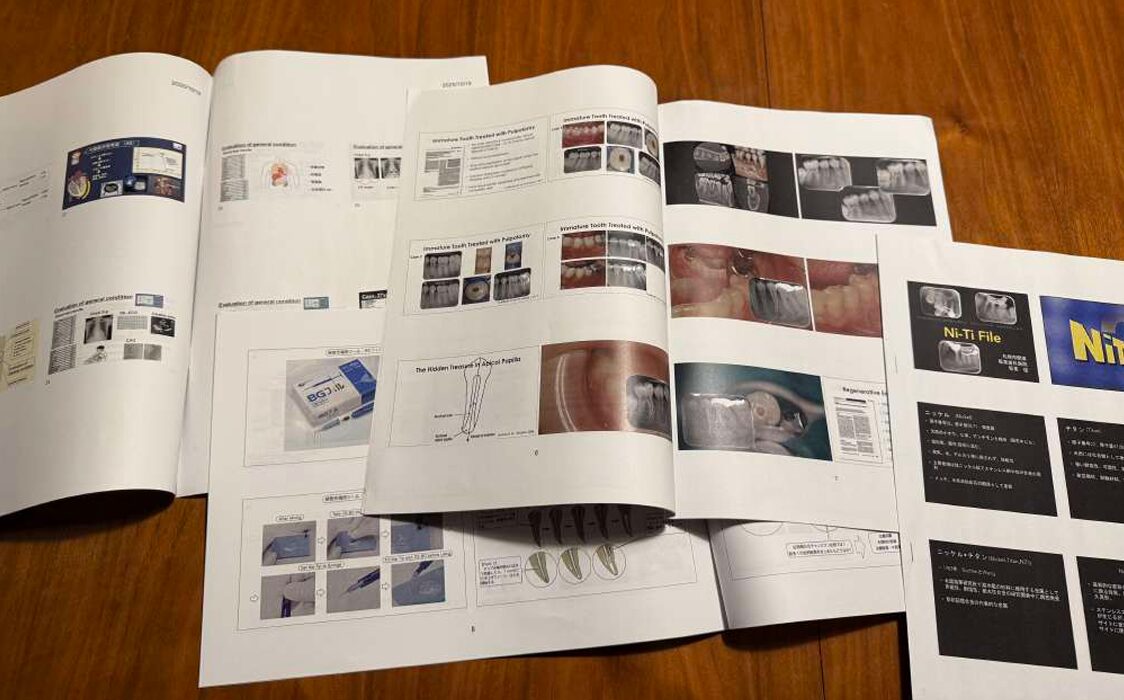
その中でも私が特に興味深く拝聴したのが、田中 利典先生による『最新歯内療法術式~近年の臨床歯内療法学におけるトレンド~』です。
ステント/ダイナミックナビゲーション/ロボットアシスト、AAE(米国歯内療法学会)の最新ポジションステートメント、そして歯髄再生療法(Regenerative Endodontics)まで、直近1年分のJOE(Journal of Endodontics)を俯瞰的に整理した濃密な内容でした。
学会において「歯髄再生」がトピックに!
講演を聞いて感じた“時代の到来”
専門医として、改めて強く感じたのは、「歯髄再生が、もはや“夢物語”ではなく、現場の選択肢になった」ということ。
基礎・臨床・制度の三本柱がつながり、再生医療が“学会の中心”に立った瞬間を感じました。
1)ナビゲーション&ロボティクスはどこまで“効く”のか?
• 用途の約8割は外科(マイクロサージェリー)領域
根尖位置の正確な確認や頬側骨のアプローチ計画に有効。
逆根管充填や骨開削の“完全自動化”までのフェーズには未到達。まだ技術的に過渡期。
• ロボット vs ダイナミックナビゲーション vs ステント(in vitro比較)
精度ではロボットがわずかに優位。
一方で時間効率ではステントが圧勝。ダイナミックは柔軟だが、実測値では差が限定的であり、“未来感”に比べて、数値上の優位は限定的という冷静な結論。
• 導入のリアル
初期投資と学習コスト(5~13症例+習熟まで20症例前後)が課題。
インプラント治療併設の複合クリニックでは投資回収が見込める一方、エンド専門クリニックでは慎重な判断が必要。
私の結論:
「ナビゲーション技術」は全例を置き換える革命ではなく、“難症例の確実性を1段上げる補助ツール”。
目的(どの症例で何を短縮/高精度化したいか)を明確にすれば、強力な味方になると思いました。
2)AAEポジションステートメントが示した“当たり前”の根拠
• 科学的に裏付けられたラバーダムの効果
これまで「当然」とされていた防湿が、患歯生存率に有意差をもたらすことが大規模データで確認。
とくにポスト付与時のラバーダムが予後を押し上げるという報告が印象的でした。
• 教育と臨床の分断を超えて
根管充填で“エンドは終わり”、築造から“補綴の仕事”という線引きは再考が必要。
築造までを防湿下で一気通貫することが感染管理の新たな標準に。
私の結論:
当院でも、仮封除去から築造までラバーダム一貫で行うように再確認しました。
「防湿一貫」は科学的根拠に基づく安心の証であると改めて感じました。
3)メインディッシュ:歯髄再生療法(RET/RED)の現在地
田中先生の講演で最も心を動かされたのが、歯髄再生療法(Regenerative Endodontics)に関するアップデートでした。
もはや研究室レベルではなく、臨床における「現実的な選択肢」として語られる段階に入っていることを実感しました٩( ‘ω’ )و
3-1 セルフリー(細胞を使わない)アプローチ
• 若年の根未完成歯で有効。根尖閉鎖・根長延長・歯質肥厚が報告され、アペキシフィケーションに代わる第一選択へ。
• 成功の鍵:感染が浅い時期での介入、軟組織温存、水酸化カルシウム貼薬、緊密封鎖。
• 組織学的には「修復」に留まることもあるが、機能回復・形態改善には十分寄与。
3-2 セルベースド(幹細胞移植)アプローチ
• 日本が世界をリード。ヒト歯髄幹細胞+G-CSF+コラーゲンで神経・血管を含む歯髄様組織を再構築。
• 評価にはEPT/冷温診に加えMRIで軟組織を可視化する工夫も。
• 課題はドナー歯の確保、施設要件、コスト。現時点では先進的な限定適応。
3-3 セルフリーの新潮流:薬剤で“惹き寄せる”
• ケモカイン受容体拮抗薬などで、細胞を使わずに再生を誘導する研究が進展。
ドナー不要・制度的ハードル低下が見込めれば、一気に普及に近づく可能性。まさに“ゲームチェンジャー候補”であり、“再生の民主化”に期待。
私の結論:
歯髄再生療法は「適切な症例選択は、すでに患者利益に直結する」段階に到達。
一方でで幹細胞移植はエビデンスと制度整備の“第二山”。安全・再現性・費用対効果を満たしつつ、限られた施設から段階的に広がるのが現実的だと感じました。
ハートフル歯科における実際の取り組み
当院(東京都三鷹市・ハートフル歯科)では、歯髄再生療法(RET/RED)をすでに臨床で実施しています。
若年の根未完成歯(外傷や中心結節破折など)ではセルフリーRETを第一選択として検討して、マイクロスコープ下での軟組織温存・最小介入・緊密封鎖を徹底。
貼薬は水酸化カルシウムを基本として、仮封除去から築造までラバーダム一貫で行うように努めています。
幹細胞移植(セルベースド)については、制度要件を満たす連携施設と共同で、適応を厳選しながら取り組んでいます。
再生療法は“未来の話”ではなく、すでに患者さんへ還元できる臨床技術であると考えています。
4)臨床における“いま使える”実践ポイント
• 中心結節破折の若年症例は早期対応が鍵:軟組織温存→緊密封鎖→短期再評価
• 防湿の徹底:根管治療~築造までラバーダム一貫
• 技術選択:ステント=速く確実、ロボ=高精度、ダイナミック=柔軟。院内事情で最適化
• 患者説明:「歯の神経を“戻す”治療が一部で可能になっています」
5)学会が“歯髄再生を第一選択に”と書く意味
AAE(米国歯内療法学会)は明確に、
“Regenerative procedures should be considered as a primary treatment option.”
(再生療法は第一選択として検討すべき)
と述べています。
これは単なる新技術ではなく、治療計画そのものの思想転換と言えるのではないでしょうか?
「削る前に、抜く前に、再生を考える」
それらの実践こそが、今後のエンドドンティクス(根管治療)の使命であると感じました。
まとめ
• 昔は「神経を取るしかない」歯でも、今は“再生して残す”選択が可能に。
• 年齢・感染の広がりなどで適応が決まります。
• 早期の受診が「歯を残す」チャンスを広げます。
• 当院では防湿(ラバーダム)を徹底して、歯の寿命を延ばす治療を目指しています。
学会において、「歯髄再生療法」がこれほど“当たり前に語られる”日が来るとは…
「抜く前に、削る前に、再生を考える」
歯髄再生療法が「選択肢のひとつ」として語られるようになった今、私たち臨床家がその実践と責任を担う番ではないでしょうか。
私たちは、そのような時代の到来を、現場から推し進めていきたいと思います。
初診予約・治療相談に関するお問い合わせはこちらから↓
三鷹・東京で精密根管治療をお探しならハートフル歯科|無菌化で再発防止
「すべては患者様の笑顔のために」
本山 直樹